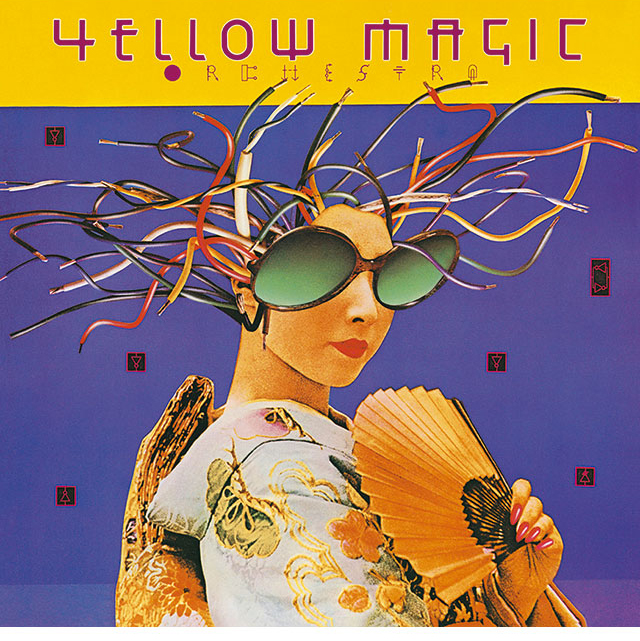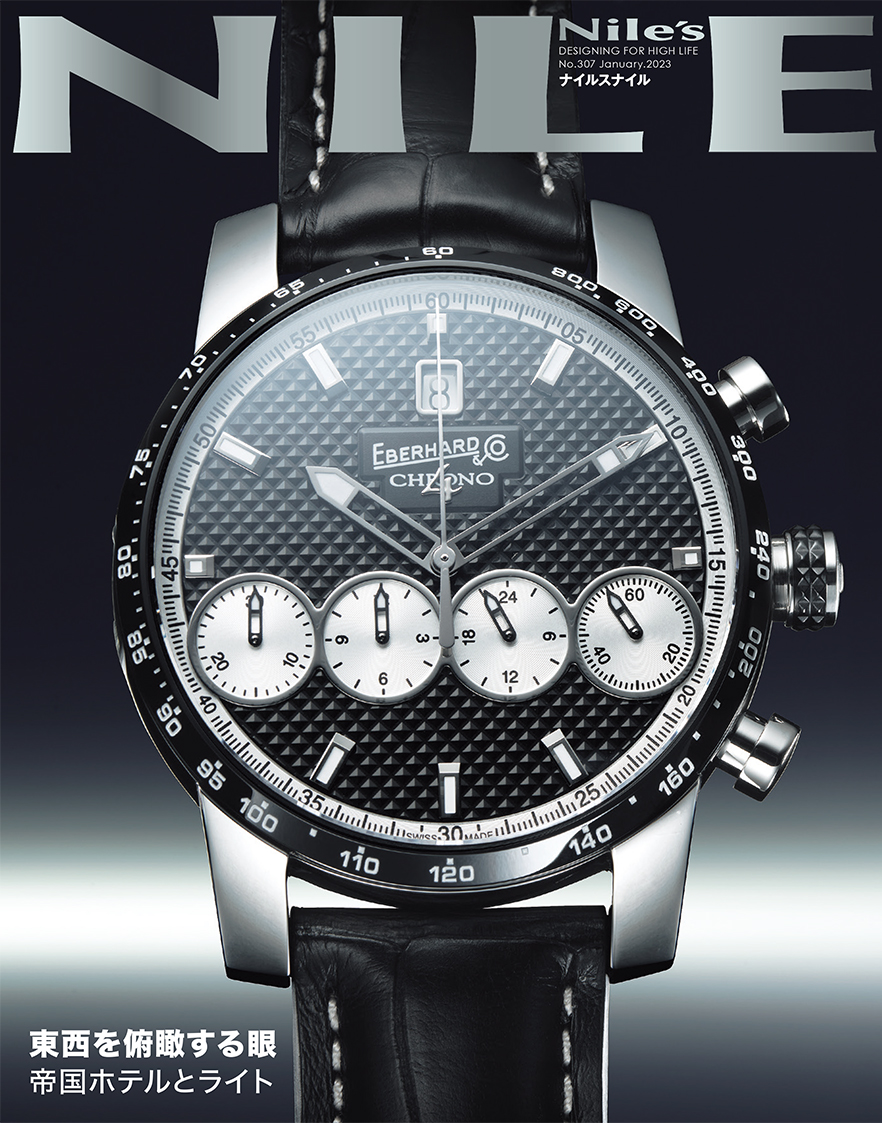大阪大学大学院工学研究科卒。94年、株式会社ブリヂストン入社。研究開発本部を経て2006年、中央研究所設立を機にタイヤをはじめさまざまな分野の素材の開発に携わる。15年に米国研究所所長、17年に中央研究所所長に就任。21年より先端材料部門長として、新素材や将来のサステナブル材料を開発する部門を指揮する。
“生まれたて”の「B-Innovation」を訪問した。まず目を惹くのは入ってすぐの「Bマーク」。ブリヂストンらしさの一つである「Creativity(創造力)」を象徴するこのロゴが、イノベーションの中心地にふさわしい光彩を放つ。そこから階段を上ったセキュリティゲートの先に、「オープンイノベーションハブ」が続く。
同社のコア技術や製品が多数展示されており、タイヤのカットモデルや、金属繊維を編み込んだ月面探査車用のタイヤ、チューブがヒトの筋肉のように伸縮するラバーアクチュエーターを使ったロボットアーム、タイヤに使われている素材など、「実際に見て触り、パートナーと交流をすることで、アイデアが膨らむ」仕掛けになっている。この空間はつまり、「共感・共議・共研・共創」の流れをつくる起点となる所だ。
また研究棟の裏には「B-Mobility」というミニテストコース。アイデアを形にしたら、すぐに実車を使って試せるそうだ。ぐるり回るうち、未来技術への期待感が高まった。
さて話題をSDGsに移そう。ブリヂストンは創業以来「最高の品質で社会に貢献」という使命のもと、現代の「サステナビリティ」に通じる考え方を経営の軸としてきた。創業者・石橋正二郎の「社会、国家を益する事業は永遠に繁栄すべきことを確信する」という言葉にも、現代社会が目指す“SDGs精神”がうかがわれる。
「我々は今、2050年にサステナブルなソリューションカンパニーであることを目指して『ブリヂストン3.0』ジャーニーに舵を切りました。創業期を『1.0』、1988年の米ファイアストン買収により飛躍的に進んだグローバル期を『2.0』と定義し、第三の創業に挑む気概をもって進んでいます。このままでいくと約30年後には、産業のあらゆる分野で使われる材料、言い換えれば地球資源が今の2.5倍に膨れあがると言われています。そこを見据えて、材料を循環させて使う『サステナビリティビジネスモデル』を構築し、最高の品質のタイヤを提供し続けていきたい。その中核を成す材料の開発に取り組んでいるのが、我々の部門です」
わかりやすく言えば「つくって売る」だけのビジネスからの脱却。「使う」「戻す」を含めたバリューチェーン全体で、寿命を終えた1本のタイヤに新たな命を吹き込むことに挑戦している。
「使う」段階では、タイヤの台は残して、ゴムの磨り減った部分だけを貼はり替える「リトレッド」が代表的な取り組みだ。「使い終わったら新品にするという形で3本使用した時と、1本のタイヤを2回リトレッドして3回使用した場合を比べると、コスト効率が良いことに加え、使用原材料が半分、製造時のCO2排出量も半減する」という。
新品志向の強い日本では馴染みにくいとされたが、保守サービスと合わせて取り組みを本格化させた2000年代後半から普及が拡大。走行距離の長いトラックやバス、離着陸時に大きな負荷のかかる航空機などで利用が進んでいる。
「戻す」段階での挑戦が「タイヤがタイヤに生まれ変わる未来の実現」への思いを込めた「EVERTIRE INITIATIVE」という活動だ。これが「古いタイヤを溶かして、また型にはめればいい」なんて簡単な話ではない。
「タイヤは石油由来の合成ゴムのほか金属のワイヤー、ポリエステルやナイロンなどの有機繊維、強度を補強するカーボンブラックとその分子の結びつきを高めるシリカなど、多くの素材が使われている非常に複雑な化合物」だから、全てを一度分離し、ある程度細かい素原料に戻さないと、現在使用している原材料と同等以上の品質のリサイクル材料を得ることは難しいそうだ。
「我々1社では、その技術の壁を乗り越えることはできません。そこで“この指止まれ”方式で、将来のサステナビリティに必要なサーキュラー・エコノミーに共感していただけるパートナーを求めています」。石油精製のプロであるENEOSはその一社。目下、この場所で「使用済みのタイヤを精密熱分解して得られる分解油を石化原料化し、さらに合成ゴムの素原料を製造するための“共研”が進んでいる」そうだ。
またガス発酵技術を持つ米ランザテック社とのパートナーシップも進展中。「ガスを微生物で発酵したアルコールから、タイヤの素材をつくる」ことを構想している。大月氏によると、「とにかく分離が大変。そこをクリアできれば、リサイクルは比較的簡単」だという。
思えば、タイヤのみならずモノが“永遠の命”を持つことは、究極のリサイクルと言える。より高みを目指すブリヂストンのこの挑戦に、サステナビリティの本質を見るようだ。